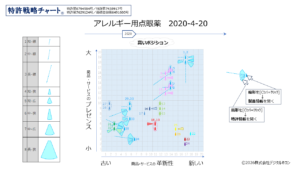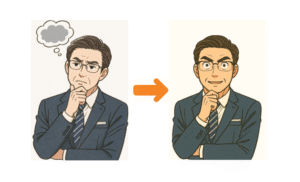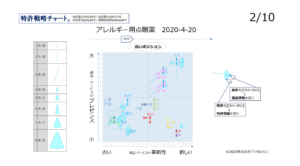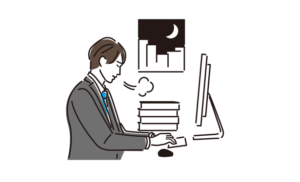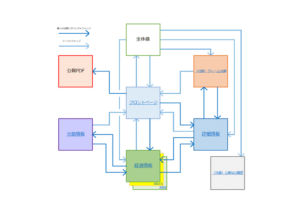無理難題と思われる事案に困ったことはありませんか?
▼多角経営の企業に所属していると、特許調査の対象は自社開発品に限らず、他社からの導入品であることが度々あります。▼自社開発品であれば、長年信頼関係を築いてきた社内の研究者・技術者が知財部の事情をおおよそ理解してくれていて、円滑に業務が進むように根回ししてくれます。これは非常に有り難いことで、助けられていることを認識し、日頃から感謝の気持ちを忘れないようにしたいものです。▼ところが、トップダウンや事業部門の提案など、知財、特に特許に馴染みのない方主導で商品導入の話が生じたときは、特許調査に関してほとんどお構いなしで話が進んだり、スケジュールが組まれてしまったりする場合がしばしばです。
無理難題と思われた事案 3選
▼筆者も多角経営の企業の知財部に17年半在籍していたので、困難な状況はそれなりに経験いたしました。その中でも、特許調査関係で無理難題と思われた事案は頻度が高く、ずっと記憶に残っています。そこで、当社(株式会社デジタルキロン)の商品・サービス開発にあたっては、そのような状況にも対処できるよう意図して取り組んでまいりました。▼ここでは、実体験に基づいて、無理難題エピソードを3つご紹介いたします。
#1 93種類の成分からなる組成物を調査対象品とするクリアランス調査(侵害予防調査)の依頼が来た
▼組成物とは、複数の原材料を配合して作る製品のことであり、例えば医薬品、加工食品及び化粧品などが該当します。製品の実施態様(仕様)は、配合している成分を表や列挙の形式で表記したものです。これに対して、組成物に関する特許のクレームは、「A成分、B成分及びC成分を含む組成物」というように特徴となる組み合わせの形式で記載されるのが一般的です。製品の成分表が、特許でクレームされた組み合わせを包含するかどうかについて対比し、当否を判別することになります。▼ざっくり言うと、シンプルな組成物であれば10種類程度の成分からなります。30種類から40種類になるとだいぶ複雑な部類と言えるでしょう。それに対して93種類は非常に多いです。成分表は何ページにも及び、同義語や上位概念の文言等を加えると情報量はかなりのボリュームになります。その中から2~6個程度を選ぶ組み合わせは約8億2000万通りに上りますから、当否をパッと判別するのは人間には到底無理です。▼初心者のうちはシンプルな組成物から始めてだんだん経験を積み、20種類、30種類にも対応できるようになるのが一般的なスキルアップでしょう。まず成分表をだいたい脳で記憶し、成分表を手元において確認しながら特許のクレームとの対比を連続的に繰り返すのが普通のやり方です。しかし、93種類となると、そのやり方は現実的ではありません。この特許のクレームには該当しない、と見切るのにいちいち不安がよぎり、なかなか次の特許に移れないという難しさがあるのです。▼私の場合は、20種類、30種類を超えて40~50種類の組成物の事案を経験した時にこれまでのやり方では無理だと判断し、Excelで成分(構成要素)のデータベースを作る方法を編み出しました。その方法を修得していたおかげで、93種類の組成物の事案がきたときも対応することができました。
#2 会社が11製品からなるスキンケアブランド丸ごとについて日本国内販売ライセンスを取得したため、一度に11製品のクリアランス調査(侵害予防調査)の依頼が来た
▼外国で開発された製品なので、日本で特許権侵害のリスクがあるかどうか調査されておらず、不明。特許補償もありえない状況。11製品なので、1製品の調査の所要時間の10倍とまではいかなくとも、4~5倍は時間が欲しいところです。しかし、特許調査は発売スケジュールの律速因子とされず、通常の1製品分の時間しか与えられていない、という条件で調査を開始しました。▼5名で手分けしましたが、各々ほかの事案も抱えているため、一斉にこの調査のみに注力することはできません。極めてタイトなスケジュールなので同じ特許を重複して査読するのは時間の無駄と考え、FIベースで作成した大きな特許集合を5つの群に分けて各人が担当する形で行いましたが、成分表を11個並べて、まずいずれかが該当するかどうか判別し、次にどれが該当するか特定するという作業は困難を極めました。そもそも、似て非なるものを含む11個の成分表を、大まかにであっても区別して記憶することがまず無理です。できる範囲でベストを尽くすというスタンスで行いましたが、正確に抽出できたかと言えば自信はないのが正直なところでした。▼一度に11製品というのは極端な事例でしたが、その後もシリーズものなど複数製品まとめて同時にスクリーニングしなければならない事案は時々やってきました。あのときの苦しい経験から、どうすれば思考の目詰まりを解消してスムーズに篩掛けできるか、ツール作りから工夫を盛り込み、実際の調査で実践する経験を重ねることで、だいぶ対応力が上がりました。
#3 実施可否調査(クリアランス調査、侵害予防調査)であっても、母集合の件数に拘わらず1週間以内に調査結果を出すよう、知財素人の組織上偉い人から命令された
▼調査担当者としては、もちろん必要以上に時間が欲しいと申し上げるつもりはありませんが、精度を高めるためには許容される範囲内でなるべく時間が欲しいという思いがあります。一方、門外漢の方にとっては、知財、特に特許調査が理解及び想像の範囲を超えた世界であるため、ご自身の職務(都合)を基準として1週間が限度とおっしゃるのでしょう。▼命令する側とされる側、立場が180°異なると交渉しようにもなかなか落としどころが見いだせず、そのうえ力関係に格差があれば、先方の口から上記のような無理難題が飛び出すこともあります。前提条件ほぼゼロで「とにかくやれ」という言い方は無茶苦茶ですが、組織の歯車としては心の中でそう思っても口には出せず、できる限りのことをやって身に降りかかるリスクを最小にするのが自分にできることでした。▼それには、クリアランス調査のタスクを細分化し、1週間以内にやるべき順に並べ、かつ、業務フローが通るようにタスクを組んで、1週間に詰め込むことを考えました。つまり、1週間やるだけやって、それでカバーしきれずに漏れがあったらやむを得ない、と腹をくくらざるを得ません。かなり厳しい状況であっても、最低限それを行えるように開発したツールが、パテントリスト型データベース「パテリデTM」のプロトタイプです。
無理難題に対処するための手段とノウハウを組み込んだ「パテリデTM」
▼「パテリデTM」は、数々の特許調査の実務において壁を乗り越えるための工夫を取り入れ、進化してきました。上記の無理難題に対処する手段とノウハウが組み込まれていますし、そのほかにも、ちょっとした効率化や疲労軽減の工夫が満載です。▼Excelファイルですからブラックボックスがなく、お客様ご自身の工夫で改良することも容易にできます。予めお伝えいただければ、お客様の工夫を反映させたものを納品できる場合もあります。
個別事案のお悩みについて、アドバイザリーも提供
▼上記のようなイレギュラーな特許調査の事案でお困りの場合は、どうぞお問い合わせください。ご相談の上、「パテリデTM」を用いてお客様がご自身で対処できるやり方をアドバイスさせていただきます。困難な状況におかれているお客様にとって解決の糸口と方向性をお示しすることになり、活路を見出していただけたら幸いです。▼なお、対応策の実行にあたり当方に時間と労力を要する作業を別途ご要望される場合は、個別見積りとさせていただきますので、何卒お含みおきください。